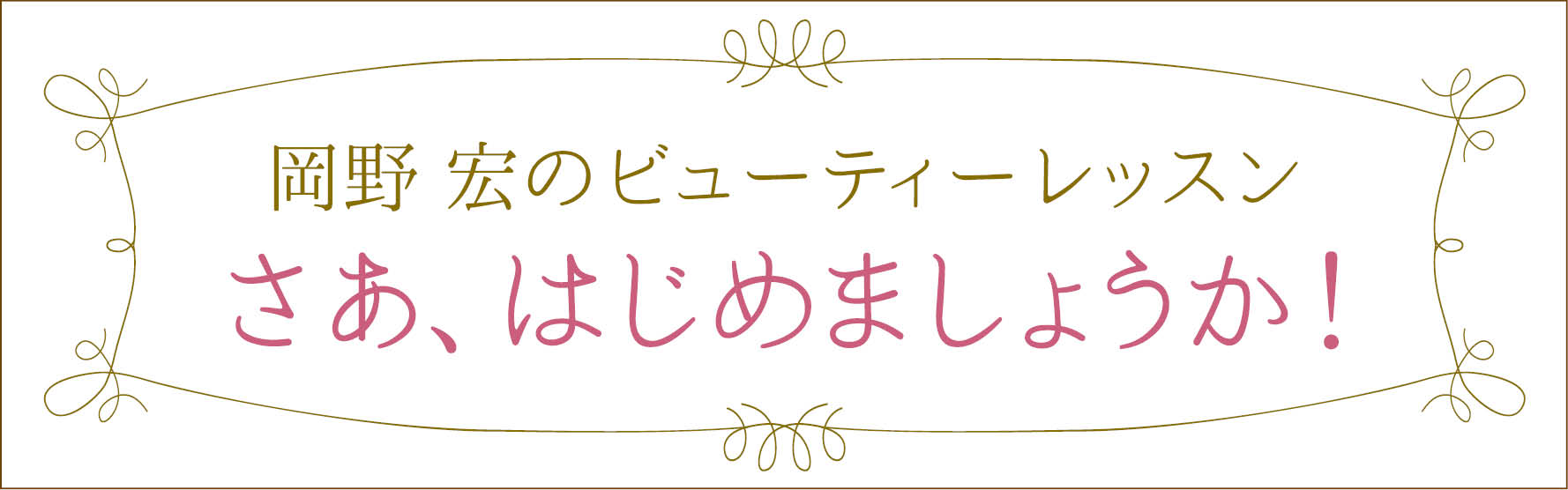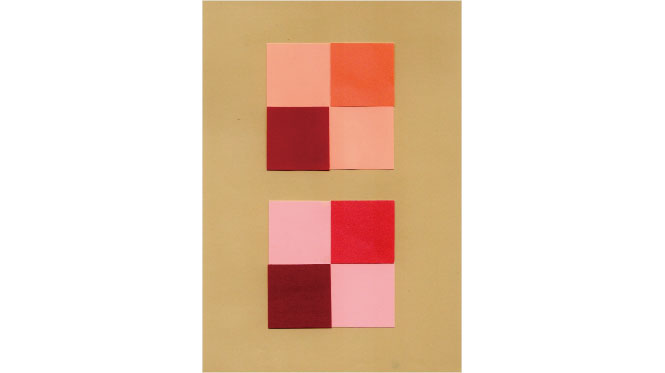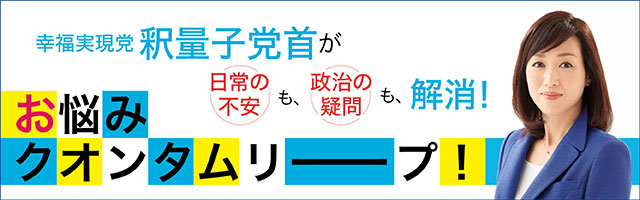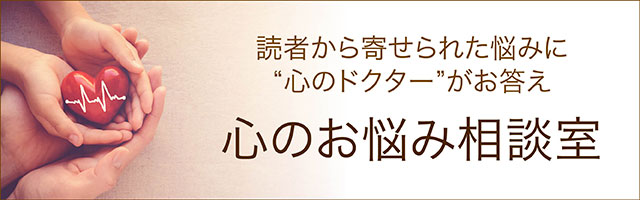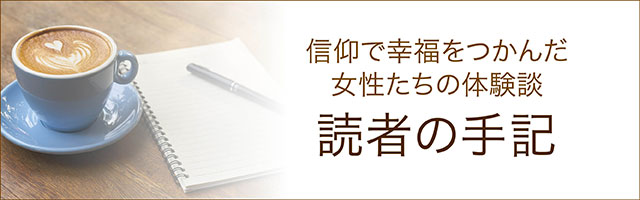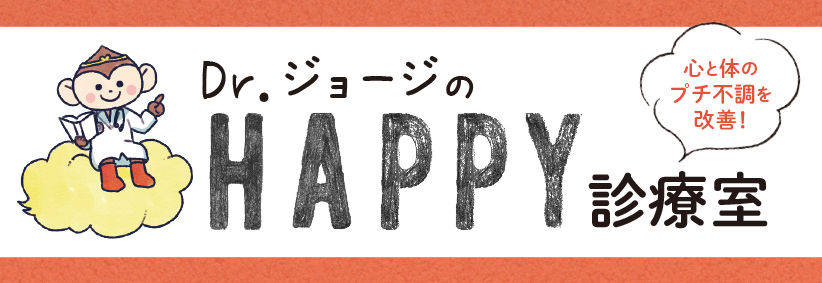画家の予言
40年ほど前、パリ在住の画家・荻須高徳(おぎすたかのり)さんが言いました。
「絵を観たり、音楽を聴いたり、感じるのに男女の差はない。こと美しく装うことに関しては、男だから、女だからという差はやがてなくなり、美しいものがいつかは認められる」
「それはパリというおしゃれに敏感な国だからで、世界に広がるのは無理なのでは」
「そう思いますか? 近いうちに日本もそうなりますよ」
その言葉通り、今では日本だけでなく、韓国などのアジアでも男がおしゃれに敏感になり、化粧をするようになりました。
男性用のファンデーション
JR中央線の中で、スーツ姿の男性3人組がデパートの化粧品売り場の話をしていました。まだ学生らしく、会社訪問のために、肌をきれいにしてもらっているようです。
「俺、3回通ったよ」
「俺も。ばれると恥ずしいから、念には念をだよなー」
美容部員にファンデーションで顔を健康的な色にしてもらい、その後自分で塗ってみて、合点の行かぬところは直し、今の状態になったそうです。鼻の横、目の周り、口の周りの細かい部分、筋肉を多く動かすところもヨレがなく、顔と首の境目も丁寧で、耳までしっかり塗れていたのには感心しました。女性の塗り方より丁寧で、きれいに塗れています。付けていることが分からない方が好まれる男性用ファンデーションは、薄くきれいに塗れるようにできています。
そのファンデーションのベースになっているのが、スポーツ用のファンデーションです。肌のあざやしみ、ケロイドを隠すためのファンデーションは早くからありましたが、それがさらに進化して、汗や皮脂に負けないスポーツファンデーションの開発につながります。自然に見え、大事な皮膚呼吸を妨げないものが完成しました。
スポーツ選手がメークに重きを置くのは、見映えが選手の人気を左右するからで、目的がはっきりしています。過去を振り返ると、男性が化粧をするのは、当たり前のことでした。
男性の化粧の目的
化粧史を紐解けば、男性が化粧をしていないのは、戦中から戦後のわずかな期間だけで、いつの時代も目的が明確です。平家の貴族、宮人たちはおしろいを塗り、眉を描き、口紅を付け、美しく装うことで権力を表しました。
戦国時代の武将が求めたのは、強さの美です。出陣のときに民衆の前で憧れを持たれ、戦場では雄々しく見えるよう、眉に墨を入れ、唇は紅を差して、白いおしろいの上を飾りました。
江戸時代は命の無事を象徴する歌舞伎役者が、時代の楽しさを化粧に表しています。そののち、文明開化を経て戦争に入り、国の方針として化粧をすることは女々しいことだと禁止され、国民服に丸刈りの姿となり、美をなくしていったのです。
戦後、男性のメークが復活したきっかけは、テレビで政権放送が始まったことです。一票を獲得するという目的を持った政治家から、封印されてきた男性の美への思いが解放され始めたのです。
目的に合わせて選ぼう
デパートの化粧品売り場には、女性用、男性用、ユニセックスと、さまざまな人たちをターゲットにした商品が並ぶようになりました。おもしろいのは、女性が男性用化粧品を自分用に購入していることです。
「女性用の化粧品でメークをすると華やかだったり、かわいらしかったり、求めているものが違ったんです。いつもよりちょっと整えたい、そんな気分にメンズの化粧品がぴったりで」
自分が求める美、何を目的にしているかを意識することで、男女問わずメークの効果は高まります。感性に男女差はありません。目的に合わせて選べば良いのです。

男女とも底辺にあるのは 美への憧れです© K’s color atelier
今月のレッスン
メークの目的を見直してみよう。
(「Are You Happy?」2022年12月号)

岡野宏
1940年、東京都生まれ。テレビ白黒時代よりNHKアート美粧部に在籍。40年以上にわたり、国内外の俳優だけでなく歴代総理、経営者、文化人まで、延べ10万人のメークやイメージづくりを行う。“「顔」はその人を表す名刺であり、また顔とは頭からつま先までである”という考えのもとに行うイメージづくりには定評がある。NHK大河ドラマ、紅白歌合戦等のチーフディレクターを務め、2000年にNHK退所後は、キャスターや政治家、企業向けにイメージアップの研修や講演活動などを国内外で行っている。著書に『一流の顔』(幻冬舎)、『渡る世間は顔しだい』(幻冬舎)、『トップ1%のプロフェッショナルが実践する「見た目」の流儀』(ダイヤモンド社)、『心をつかむ顔力』(PHP研究所)等。