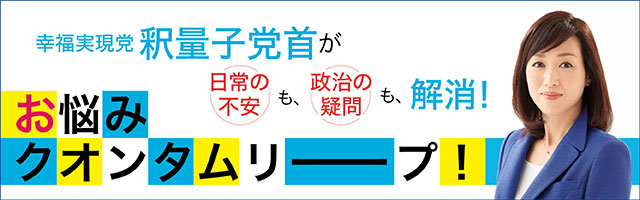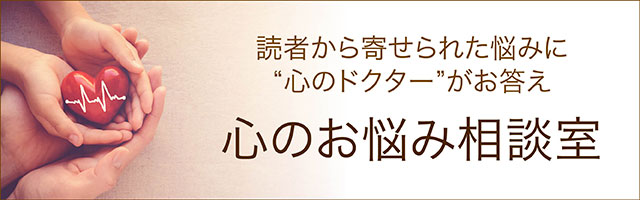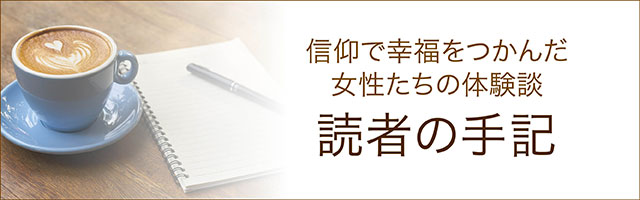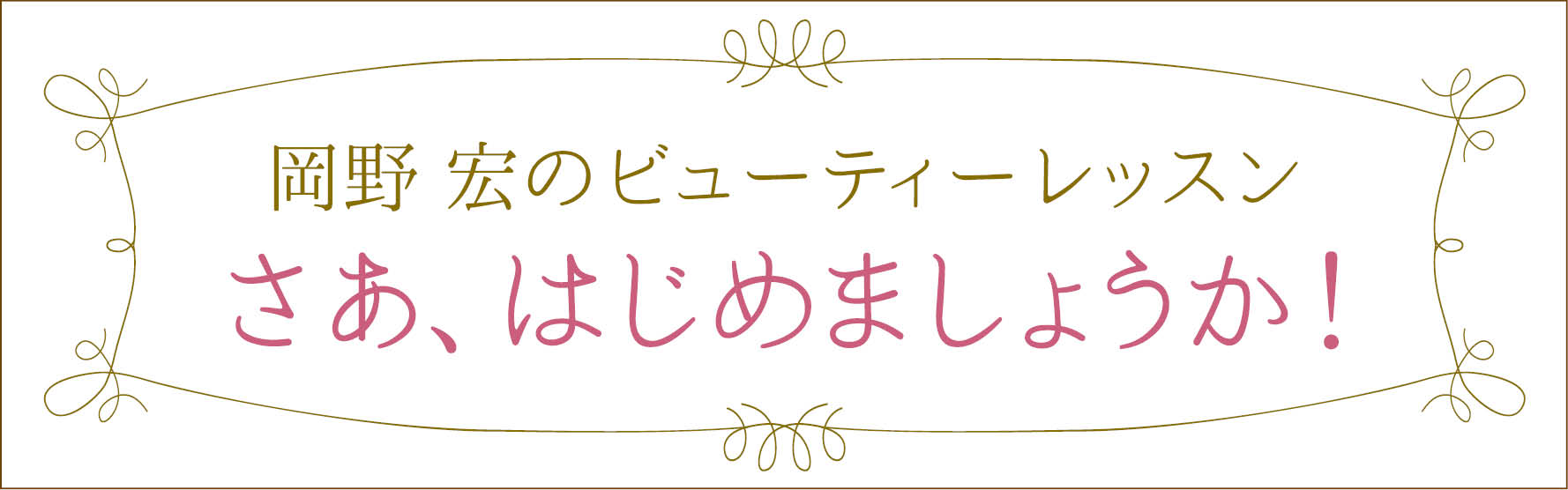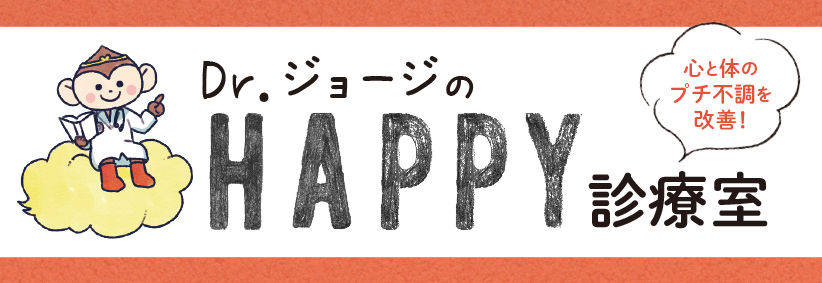今回は、大川隆法総裁の未就学児向けのお話「自助論の大切さ」のポイント解説2回目です。
子供たちの「じじょろん」
まずは、自助論を学んだ子供たちの素敵なエピソードをご紹介しましょう。
エンゼルプランV東京本校の年少から年長の各クラスでは、早速「自助論の大切さ」をお勉強しました。
クラスが終わってみんなが遊び始めた放課後、年長の男の子2人が、片付けをしている先生のそばに来て、「何か手伝うこと、なあい?」と聞いてくれました。それから20分間、2人は自分たちが使った教材を一生懸命磨きました。お友達の分まで磨きました。「たくさん磨いて疲れたでしょ。もう遊んでいいよ」と言っても、2人はうれしそうに笑いながら頑張り続けます。次の週も、その次の週も、放課後のお手伝いは続きました。
「みんなは、大人の人にいっぱい助けられたり、迷惑をかけたりしながら育ててもらっているんだよ。だから、お母さんや園の先生が助かること、楽になるようなことをできる子供になろうね」という大川総裁のお話を、早速実践しているのでしょう。
そのうちの一人のM君は、幼稚園でこんなことがあったそうです。お片付けの時間になって、「やらないと先生に叱られるからなぁ」と言いながら、嫌々おもちゃをしまっている子がいました。M君はその子に、「あのね、お片付けは『じじょろん』なんだよ。自分で遊んだものは、自分で片付けるんだ」と言いました。すると、それを横で聞いていた別の男の子が「それ、わかりやすーい!」と納得していたそうです。
「じじょろん」は子供を成長させる魔法の言葉
いま全国の教室の子供たちとママたちの間で、「じじょろん」が話題になっています。大川総裁が作った歌「自助論で行こうよ」を毎日聴いているお友達もたくさんいて、ママたちは、この歌に随分助けられているようです。
エンゼルプランVのお帰りの時間になると、「もっと遊んでいたーい!」といつも泣いてしまう2才の女の子がいるのですが、ある日、ママがそっと耳元で「じじょろん」とささやくと、なんと、涙を拭いて立ち上がり、自分で靴をはき始めました。これには先生方も驚きました。ママに「どうしたんですか?」と聞くと、「うちの子、『自助論で行こうよ』の歌が好きで、家でいつもかけてたんです。そしたら自分で『じじょろん、じじょろん』と言うようになって、試しに今『じじょろん』ってささやいたら、この通りです」
キラキラ光るよい言葉や、よい歌には、魔法のような力があります。「じじょろん」という言葉は、どうやら子供たちをぐんぐん成長させる魔法の言葉のようです。
言葉の意味はたとえ難しくても、繰り返し繰り返し、その言葉を唱えたり歌ったりすることで、大事なエッセンスがいつの間にか子供の心と体に沁しみ込んで、子供を成長させるのでしょう。
「実は、子育てが苦手なんです」「上手にしつけができなくて困っています」そんなママにこそ、自助論のお話や歌がおすすめです。
みなさんもぜひ「じじょろん」の魔法を実体験してみてください。
(「Are You Happy?」2021年1月号)

奥田敬子
早稲田大学第一文学部哲学科卒業。現在、幼児教室エンゼルプランVで1~6歳の幼児を指導。毎クラス15分間の親向け「天使をはぐくむ子育て教室」が好評。一男一女の母。