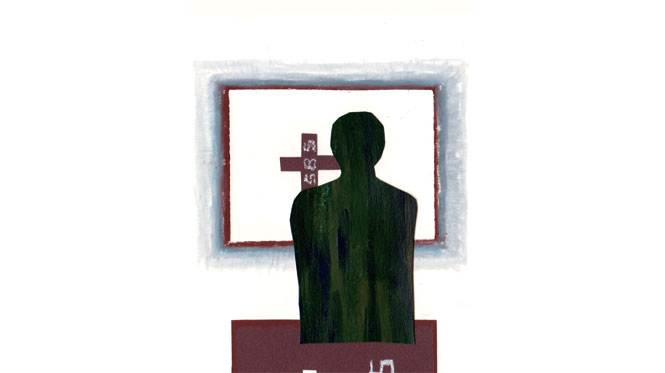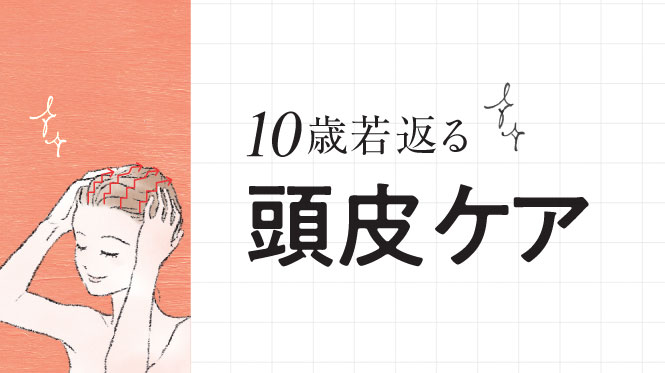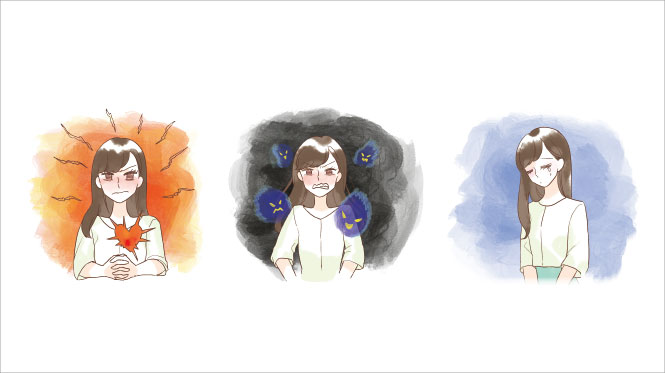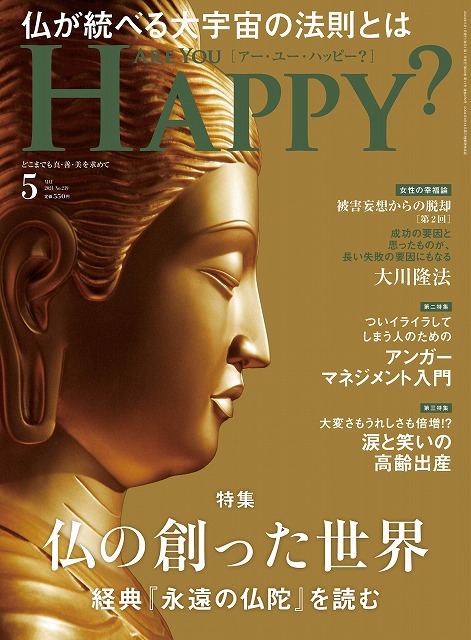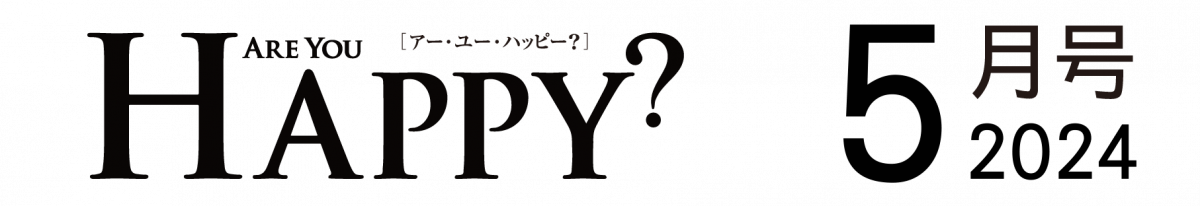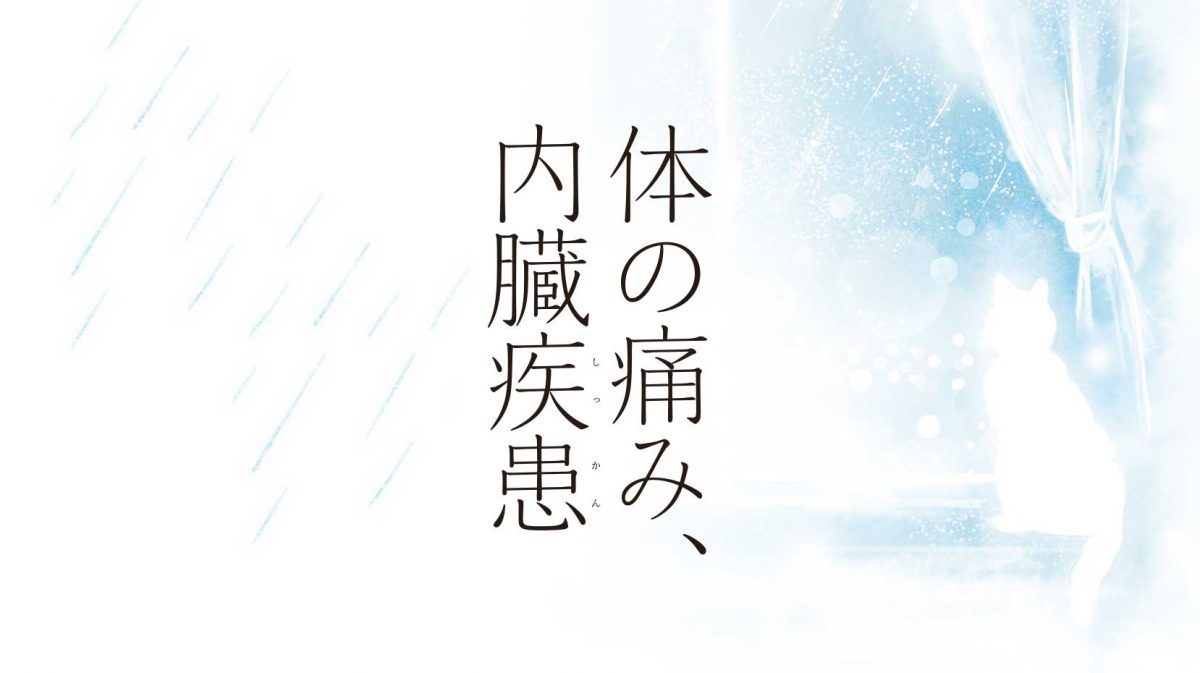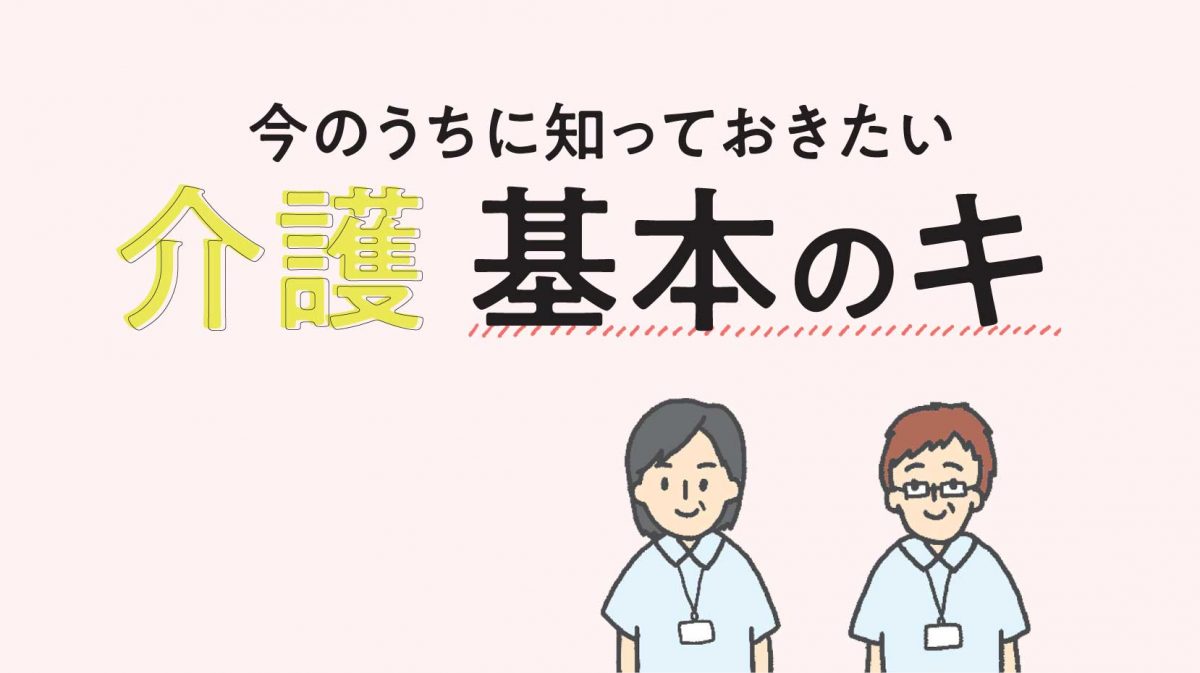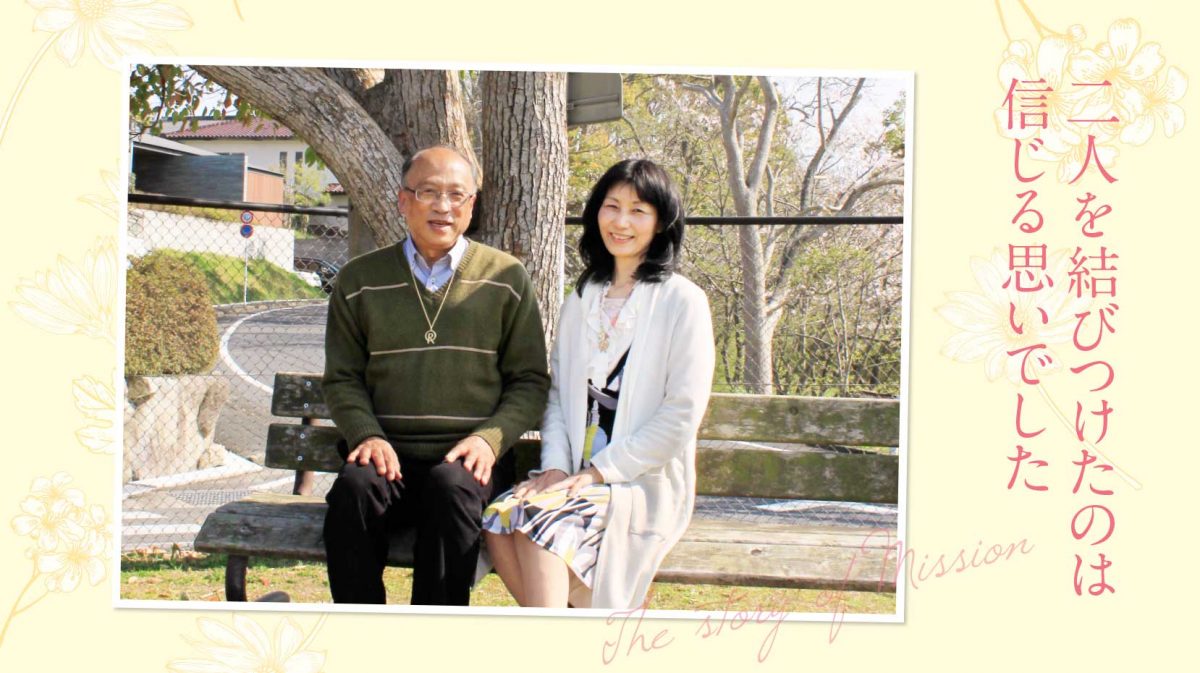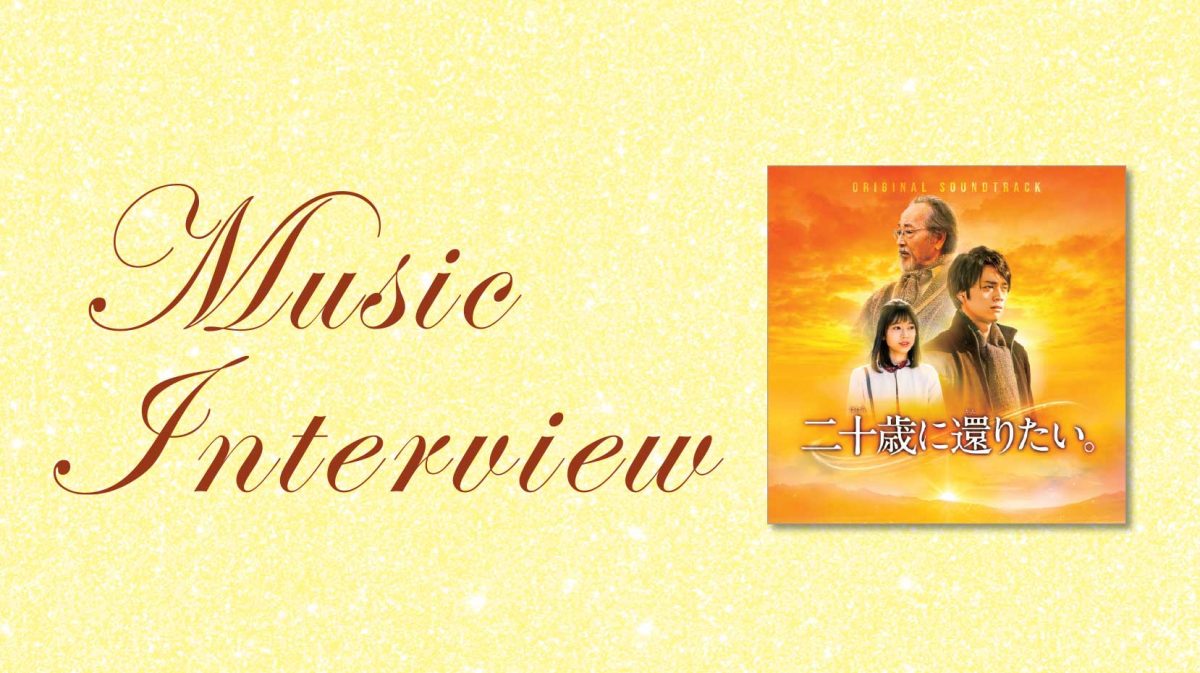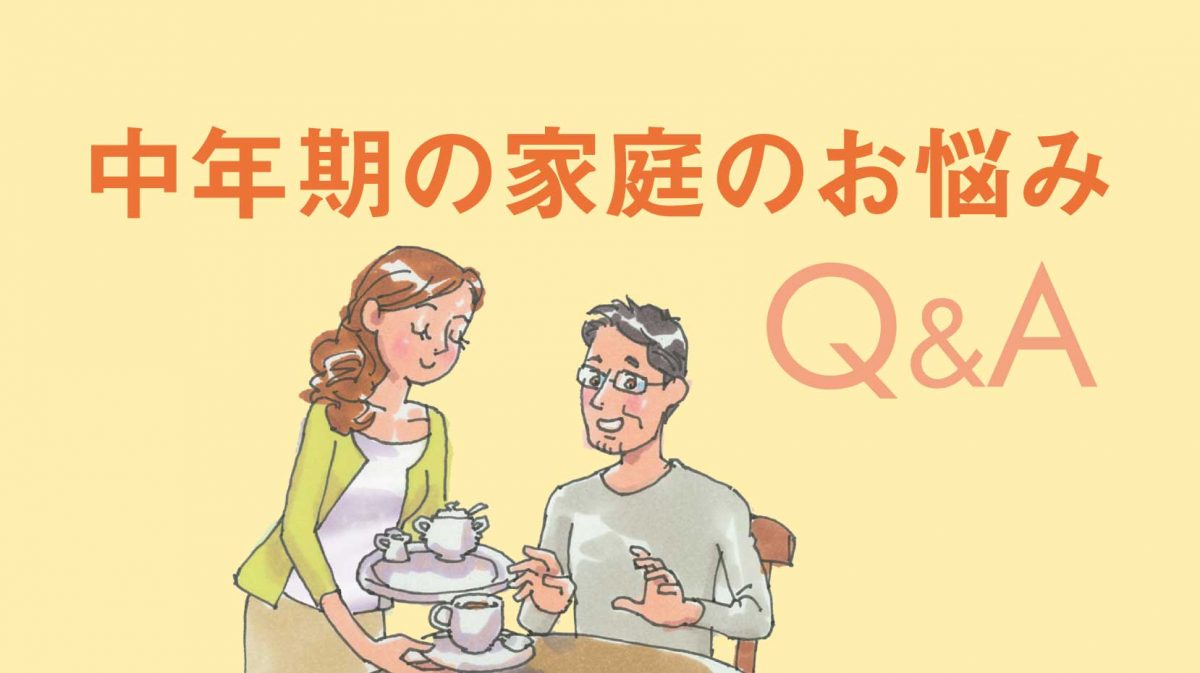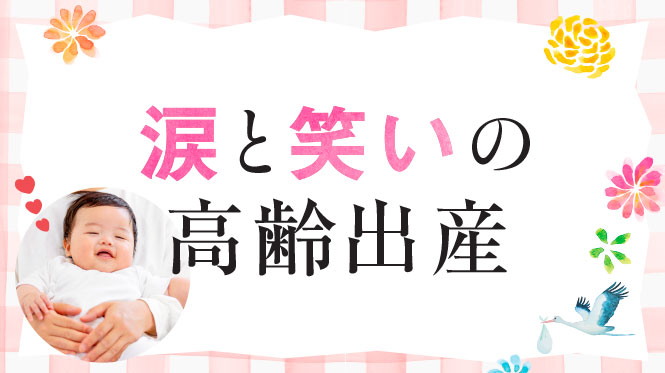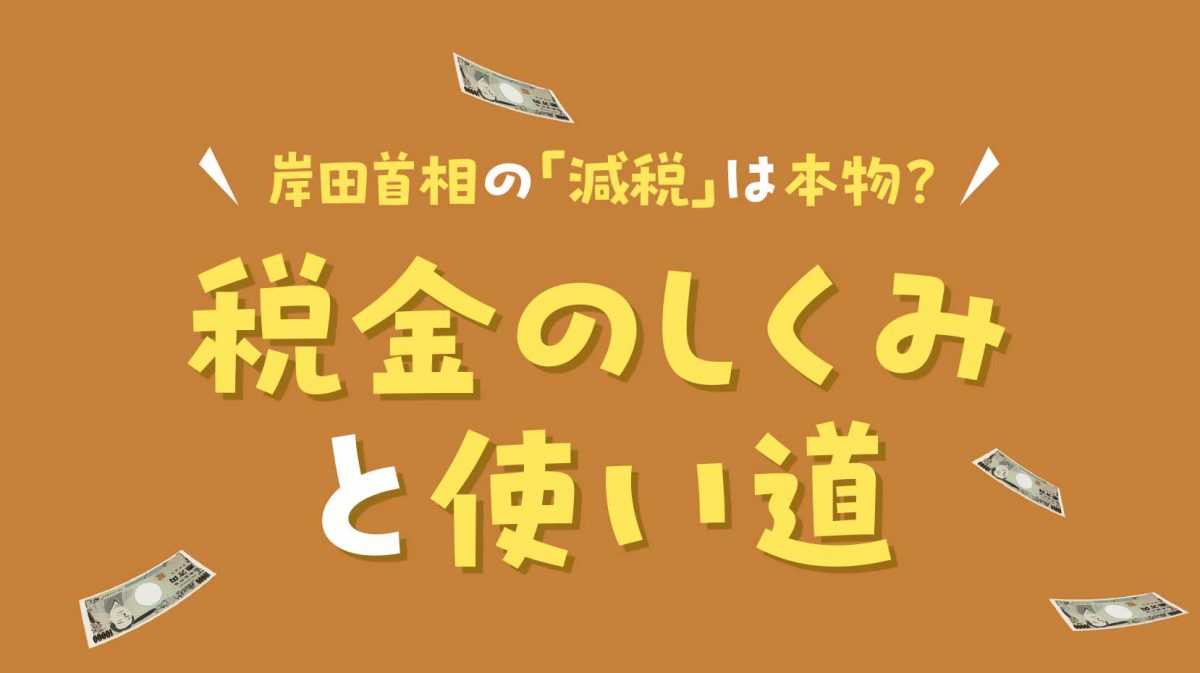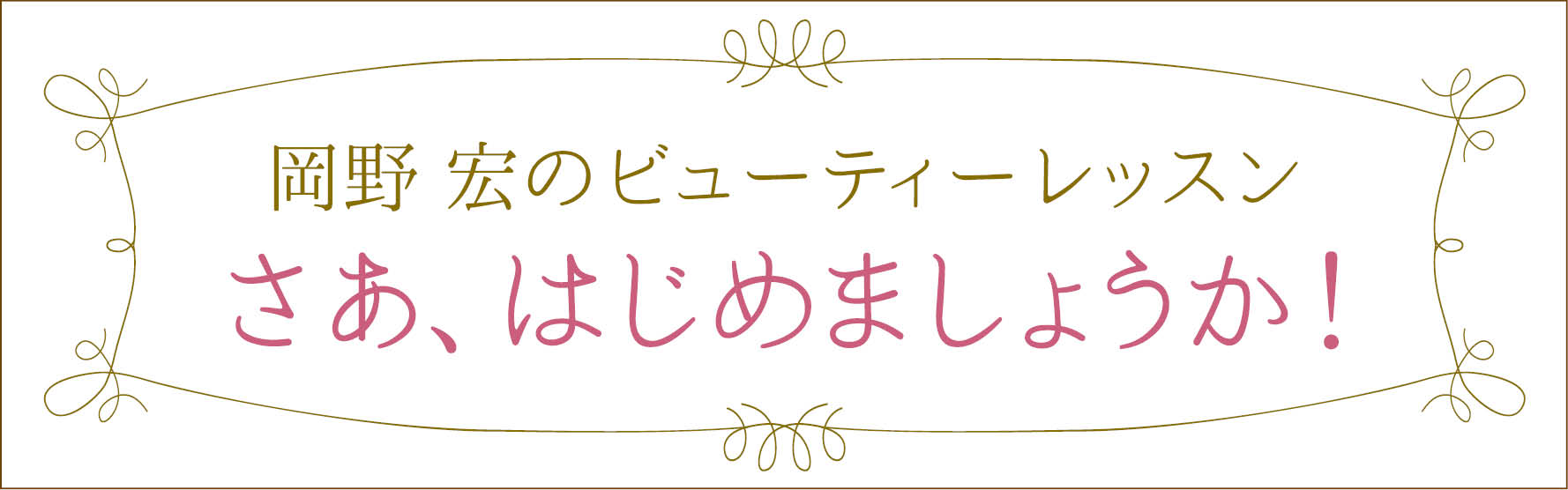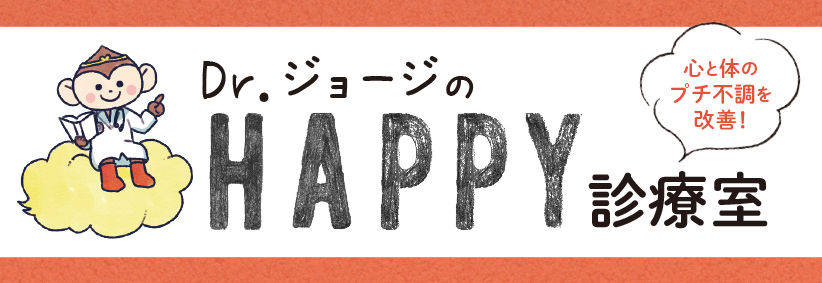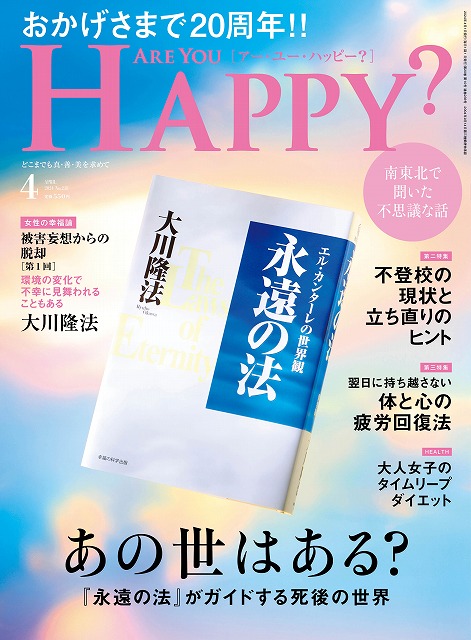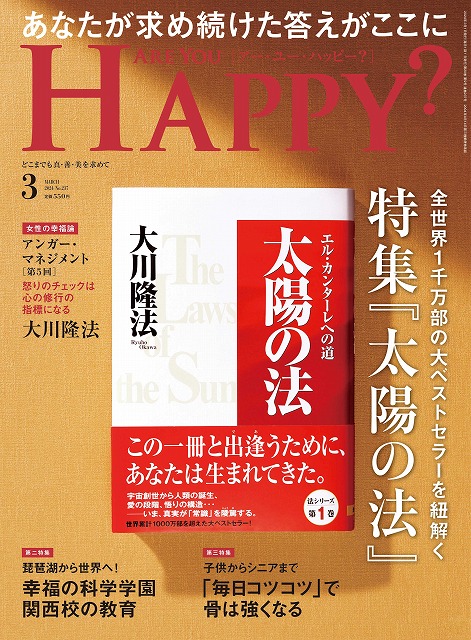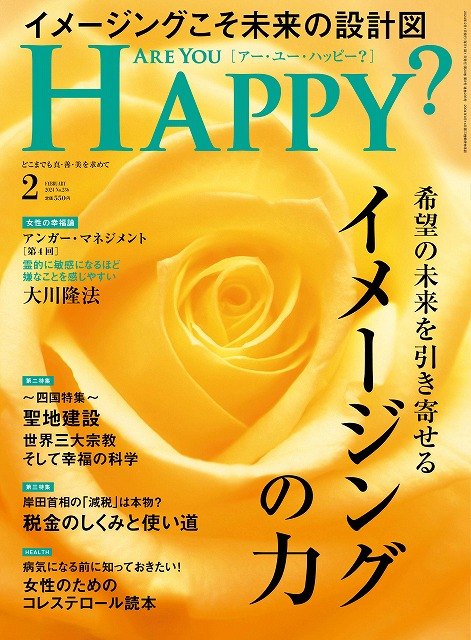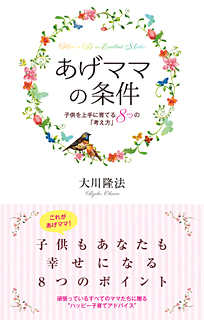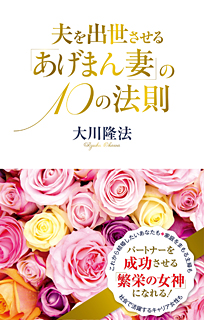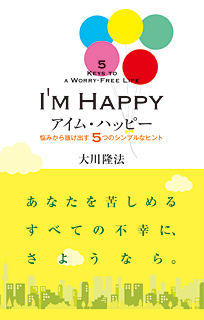- Dr.ジョージのHAPPY診療室
- お知らせ
- 一般記事
- 病気
- 介護
- 信仰体験談
- MUST GO!
- ニュース
- スペシャルインタビュー
- ライフスタイル
- スピリチュアル
- 結婚・夫婦
- 子育て
- 人間関係
- ヘルス&ビューティ
- 歴史・社会・政治
- 仕事
- レシピ
- チャート
- 幸福論シリーズ
- 連載
- 幸福実現党党首 釈量子のキッチン政経塾
- 幸福実現党党首 釈量子の東奔西走!
- 竜の口法子校長の熱烈エール「もう大丈夫!」
- 岡野宏のビューティーレッスンーさあ、はじめましょうか
- 子育て110番
- 釈量子のお悩みクオンタム・リープ
- 時代を創った女性たち
- 心のお悩み相談室
- 読者の手記
- 特集
- 人気記事
- 今月の占い
- プレゼント
- 編集部のオススメ